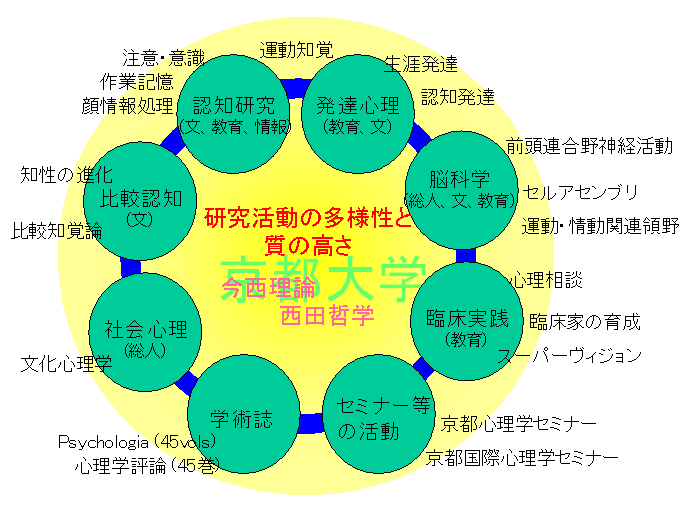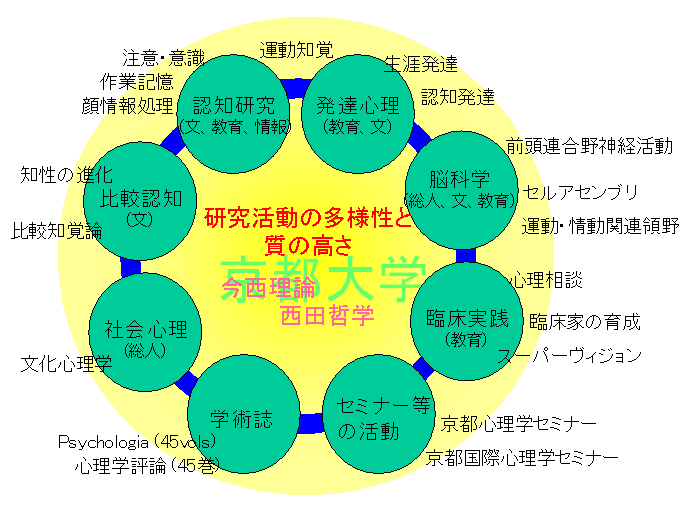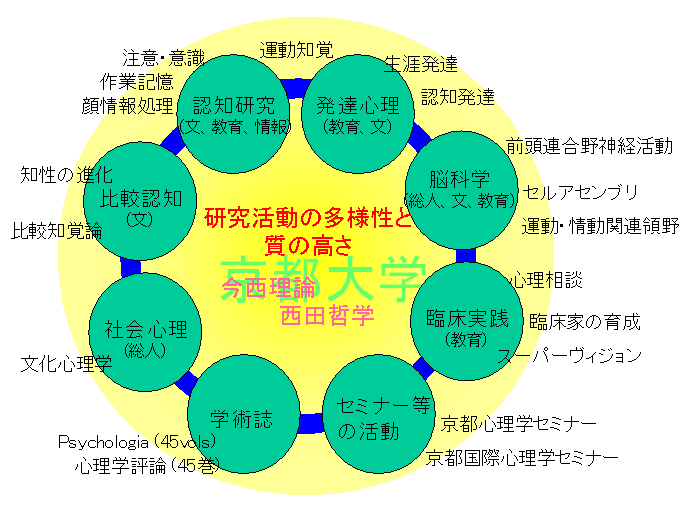本研究教育拠点の目的
21世紀は「心の時代」になるであろう。情報化社会によるグローバリゼーションや少子高齢化など、人類がかつて経験したことがない状況が急速に到来している。物質文明の進歩が人間の幸福に直結しないことも明確になり、未来の予測が困難な中、人々の心は乱れ、さまざまな社会的問題を生んでいる。このような時代にあって心理学の責務は大きい。この緊急かつ重要な責務を果たすべく、我々は、実験科学、フィールド科学、臨床実践科学の連携により、融合科学としての心理学を志向し、新たな知の方法論を切り拓くとともに、未来を展望できる21世紀の人間観を創出し、それらを国際社会に向けて具体的に発信する。
後述のように、京都大学においては、認知心理学、発達心理学、比較心理学、社会心理学、脳科学、臨床心理学等のあらゆる分野において優れた研究・教育をおこなってきた。国際的学術誌への論文掲載、学術書の出版、若手研究者の育成はもちろん、各種科学研究費の他、未来開拓学術研究推進事業、科学技術振興調整費などの大型研究プロジェクトにおいても中心的な役割を果たしてきた。多数の国際共同研究が継続的に実施されており、その活動は国内外に高い評価を得ている。しかし京都大学の心理学における最大の特色は、その相互の協調体制にある。心理的諸機能の認知科学的・脳神経科学的研究からフィールド心理学的研究、動物を対象とした比較認知研究に加え、年間5800件を越える心理相談を行っている臨床実践活動に至るまで、多様な心理学領域を専門とする40名に近い研究者が、教育・研究両面での柔軟な相互作用によって、独創的成果を生みだしてきた。これは西田哲学や今西学派などの独自の基盤を持ち、個性や多様性を重んじつつ互いに協調し切磋琢磨していく京都大学なればこその特色といえる。すでに我々は、30年以上の歴史を持つ心理学教官連絡会という月例の会合を通じて、常に情報を交換し、学術的交流を深めてきた。2000年には日本心理学会を共同で開催し、翌年には同連絡会編の書籍を出版した。教育面では、数多くの講義を相互履修可能な共通科目に指定し、学部学生や大学院学生が部局超越的な指導を受けられる体制を作ってきた。本拠点形成計画において、我々はこの伝統をさらに飛躍的に発展させ、現在多数の研究科に分散している関連講座を束ね、ヴァーチャルな研究科のように機能する連合組織−心理学連合−を構想した。このような部局超越的な教育・研究環境のもとで、今後5年間に取り組むべき共通の問題空間として下記に挙げる3項目を設定する。この問題空間に対し、実験からフィールド、臨床に渡る多様なアプローチにより相互に連携しつつ研究を推進し、欧文による学術論文や書籍の公刊、国際シンポジウム、定期的な研究者、大学院生の相互国際交流などを通じ、心理学の世界的研究拠点として、その成果を発信する。またその成果を踏まえた臨床実践活動を通じて、広く社会に資する貢献を目指す。さらに、言語学、社会学、人類学、精神医学といった隣接領域との相互作用により、より総合的な人間学への道をも探る。